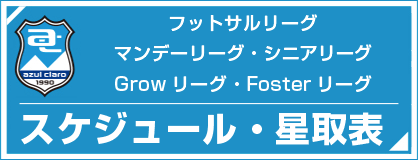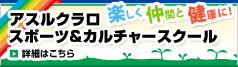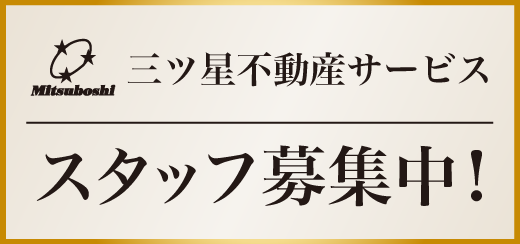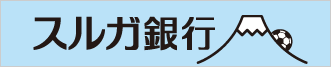【クラブ創設35周年記念手記:16回目】山本昌邦氏

「沼津から世界へ」
アスルクラロ沼津というクラブの原点は、創設者で私の弟でもある山本浩義とその仲間が、幼稚園を訪ねて園児向けに始めたスクールにあります。その子たちが一学年ずつ成長する度に小学生からジュニアユース(中学生)、ユース(高校生)、そして社会人とチームがつくられ、サッカーだけでなく、テニスやチアリーディングなど他の競技も楽しめる総合型のスポーツクラブへと発展していきました。下から、下から、チームを積み上げて行き、ピラミッドの頂上のようにプロの世界で戦うチームが最後にできたという意味では完全なボトムアップ型であり、まずプロチームありきのトップダウン型から始まったクラブが多いJリーグにあってユニークというか、胸を張れるところだと思っています。
35年のクラブの歴史の中で大きな転機になったのは、2014年にJリーグが3部のJ3を新設したことでしょう。東海リーグから日本フットボールリーグ(JFL)に上がったばかりのアスルクラロの経営陣はアマチュアの世界で満足するか、プロの世界に挑むべきか、大いに悩みました。最終的に弟たちは、J2より一つ下のカテゴリーができることをプロ参入の好機と捉えて沼津からチャレンジする道を選びました。
Jリーグを目指すのならクラブをきちんとした株式会社にする必要がある。そのスキームづくりやノウハウの伝授に、スルガ銀行の岡野光喜社長(当時)をはじめ、多くの人たちが力を貸してくれたことは、いくら感謝してもしきれないことだと痛感しています。
J3参入の競争相手がいる中で〝お墨付き〟をもらうための苦労はいろいろありました。最初に述べたボトムアップ型の総合スポーツクラブという在り方はJリーグ本部のヒアリングでも高い評価を受けました。しかし、JFLで1試合平均2千人の観客を集めるようにと注文をつけられた時はハードルの高さに青ざめました。
2017年にJ3に参戦した後、ホームスタジアムの照明が暗く、このままではJ2ライセンスの基準を満たさないのでJ3の資格を失うとなった時も同様でした。基準を満たすには億単位の改修費用がかかると知り、頭を抱えました。
ありがたいことに、改修費用の方は行政の支援やクラウドファンディング、企業版ふるさと納税などに助けられ、資金調達のメドがなんとか立ちました。
観客動員で貢献してくれたのは現監督の中山雅史です。2012年シーズンを最後に札幌で現役引退を発表しましたが、会うたびに「引退したわけじゃないですよ」と話すゴンに「本気だな」と感じ、「JFLでいいのなら舞台を用意するよ」と伝えました。2015年に沼津で現役復帰を表明し、最初の試合で彼の勇姿を見たさに8千人を超すお客さんが詰めかけたときは本当に驚きました。集客に苦労するチームの認知度を確実に上げてくれた、間違いなく功労者の一人です。
静岡の東部地域は、サッカーどころ中部の清水や藤枝、ジュビロ磐田がある西部に比べて「サッカー不毛の地」と長年、見なされてきました。しかし、プロのクラブや有名な高校サッカーの強豪校といった受け皿が乏しかっただけで、選手レベルでは川口能活や小野伸二、高原直泰、内田篤人らそうそうたるメンバーを日本代表に送り出してきました。彼らのようなワールドカップで戦えるタレントを、この地域から再び輩出することは決して夢物語ではないはずです。
トップチームには着実にステップアップしてJ1を目指してほしいですが、同時に、このクラブには地域に根ざした存在として、子供たちの夢づくりやコミュニティーの活性化に貢献する初心をいつまでも大事にしてほしいと願っています。
子供が夢を持ち、育てられるような環境を大人は整え、それを後押しする。老若男女が一緒になって地域で夢を追いかけ、それを生活の中に溶けこませて文化にしていく。国と国、人と人の間になにかと壁を築きがちな今日このごろだからこそ、スポーツを通して世界とつながり、海の向こうにこちらから出かけたり、あちらから招いたりしながら、人の行き来を盛んにするクラブの価値は、これからもっと輝きを増すと信じて疑いません。
人が行き交う、にぎやかな地域の中心にスポーツがある。いつの日か、アスルクラロがスペインのFCバルセロナのようになる。このクラブの次の35年の目標であってほしいと心から思っています。
山本昌邦